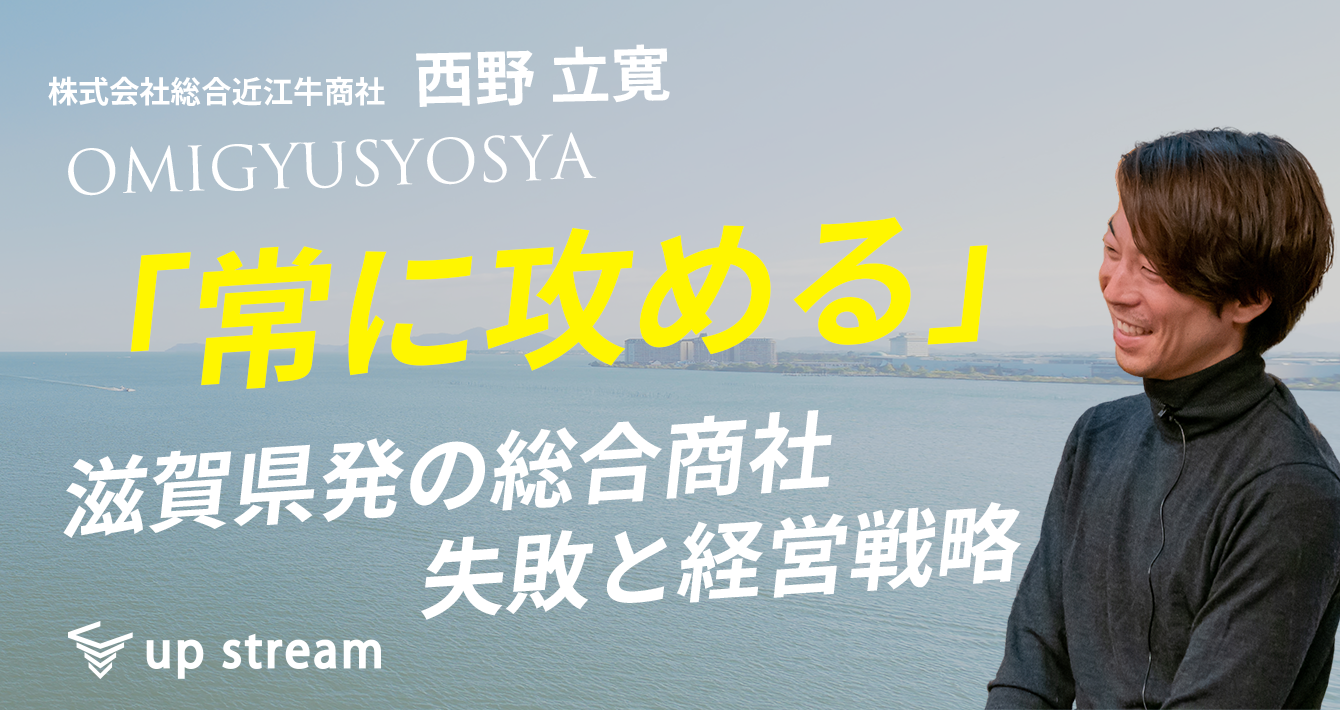前編に引き続き、株式会社総合近江牛商社 代表取締役社長の西野立寛さんにお話を伺いました。 後編では、失敗したことや現在学生の方へのメッセージをお届けします。
離職率10%の定義が生まれた経緯
ベンチャー企業である総合近江牛商社。 “よく働きよく遊ぶ”組織だからこそ、おそらく今の世の中と逆行している部分もあると語る西野さん。 過去の失敗経験について聞いてみました。
創業から間もない頃、リタイアしそうになっているメンバーに手を差し伸べることができなかった。 人が離れていった。これが、僕の中でトップクラスの“やってしまった”経験です。 飲食業はヒューマンビジネスですから、人ありき。 ただ、離れていくメンバーも、うちの会社にピタッとハマらなかっただけ。 他の会社ですごく活躍するメンバーもいると思います。これはもう相性の話。 選択肢を設けてあげることができなかったという意味では、糧になっています。

そこで生まれたのが、離職率10%の定義です。 11%だと組織が厳しすぎる。9%だとぬるすぎる。 さらに「10%ならセーフ」ではなく、「10%は退職しなければいけない」との考え方。 近江牛商社の決算は10月末です。そのため、年度末に近づく夏は、西野さん含む役員からの負荷の掛け方が尋常ではないそう。
筋トレでいうと、最終的な追い込みです。 でも、ここで離脱していくメンバーは、来季は残れない。残れたとしても活躍できないと考えています。 うちはベンチャーですから、負荷はあって当然。逆に、ないといけない。 一概には言えませんが僕は、ティール組織、いわゆる個人の能力の集合体は組織としては成立しないと思っているタイプです。 松下幸之助がつくった組織論通りの教科書的な経営を目指しています。

この考え方の元になっているのは、株式会社匠工房の関会長に相談した際に、聞いたお話とのこと。 マネジメントのロールモデルとして参考にしているそうです。
常に攻める。攻めれば攻めるほど守りが頑丈になる
FC事業、店舗展開など、順調に事業を拡大している印象の西野さん。 資金面に関しても、攻めの印象が強いです。
1年ぐらい前まで、崖っぷちギリギリで常に走り続けていました。 持論ですが、ビジネスマンが億万長者になれるかどうかは、人生かけてオールインができるかどうか。 僕はどちらかというと、オールインができちゃうタイプ。 出店が相次ぎ、ギリギリの中でこれまで走ってきている事実があります。

確率論をあげるための知識、マーケティング、マネジメント、ファイナンスに関して得意な人材を集めたり、 西野さんも含め会社として学び続けたりといった状況を前提として維持しつつ、基本はオールイン。実際の心境は。
やるしかない状況なので、心に余裕はなく、常に攻めています。 当然守りは必要ですが、常に攻めているから、いつの間にか守りが頑丈になっているんですよ。 子どもの遊びにも言えることですが、ルールがないと面白くないじゃないですか。 「守り=ルール」だとしたら、攻めれば攻めるほどルールは絶対に必要になってくる。 勝手に守られているという意味でも、攻めているということです。あと、守りを固めるためには、時間をかけません。

ディフェンス、オフェンス共にガンガン進める西野さん。 オールインする中での失敗談についても聞いてみました。
フランチャイズビジネスは、資金調達の一手段。 資金調達に一生懸命になりすぎたがゆえに、直営店の本丸の足元が揺らぐ。 これは実際あったかなと思いますし、今も実際あると思います。

本丸が揺らぐといっても、売上減少ではありません。 リアルなお客さんの声がアルバイトさんのもとで止まっていた状態。 そこからいかに引き上げるか。 その改善実行スピードを上げていくことの重要性に直面したといいます。
フランチャイズを展開し、広げるためには、目や手が取られます。 実店舗側のサービス、お客さんの声をメインに語る場が減っていた事実はあると思います。 この点に関しても、2021年後半から、重点的に改善し、今も継続中です。 2022年の初めに入ってきた即戦力の中途メンバーは、比較的サービス業や教育に特化しているメンバー。 実際、アルバイトさんも、より加速度的に成長していると思います。

個人的に感じる飲食の難しさは、売り上げが決して均一にならないことです。 しかし、安定したサービスと質。ヒューマンビジネスとしての教育、一律化。 このバランスが整えば近江牛商社の全国展開は、とてもスムーズに進む印象を受けます。
そうですね。そもそも、比較的国内ではFCモデルの展開は少ないです。 我々が食材をFCさんに卸して、食肉卸として販売。 さらに人材面に関しても、本部で仲間として加わったメンバーが各都道府県のフランチャイズオーナーの会社に飛び込んでいく。 ある意味派遣型。 そうすることで福利厚生、給与の賃金テーブル、キャリアアップが全国で統一されていく。 その結果、均一均量均質のサービスや商品の提供が、より可能になっていく。 この方法は、僕が知っている限り、国内だとマクドナルドさんぐらいかなと。
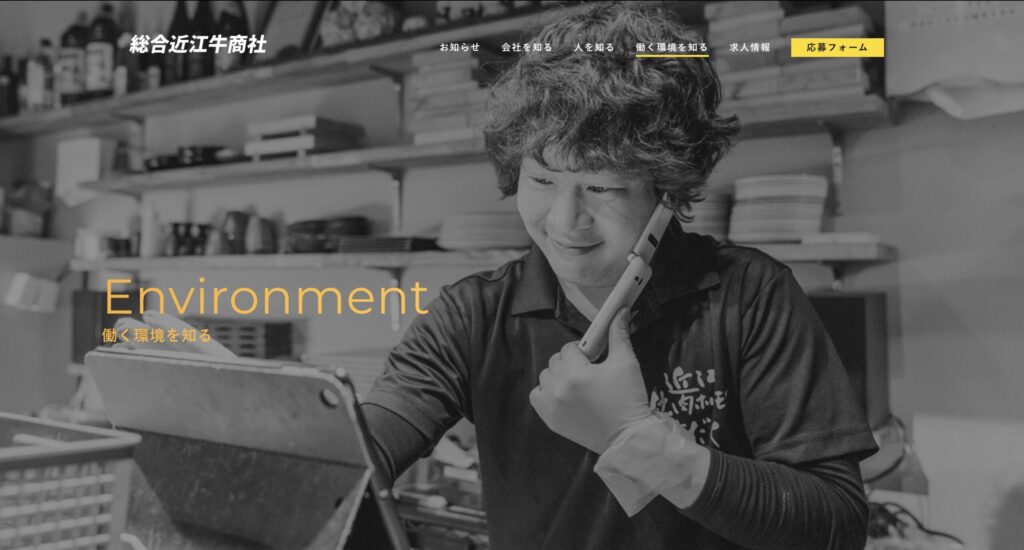
本部の雰囲気、スピリッツを持ち、共通言語を持つ人が各地に行くからこそ、各店舗で同じ意識を持つことが可能になります。 これは、中小企業である近江牛商社の強み。 経営理念がありクレドがあることを体得しているメンバーが店舗運営をすることで、アルバイトさんの質も高まると言えそうです。
株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO」の活用
資金調達には、さまざまな方法があります。 その中で株式投資型のクラウドファンディング「FUNDINNO」を行った理由についてもたずねてみました。
経営理念として、「近江牛商社で働いている人間の見聞録の最大化を目指す」との考えが基本にあります。 「FUNDINNO」もその一環だと思ってもらえるとわかりやすいかと。 銀行から資金調達するデッドは、すでにみんなが経験しています。 プレゼン、事業計画書の作り方、キャッシュの流れを資料作成する、など。 でも、エクイティの領域は、まだ経験したことがなかった。だから経験する。これが理由です。 VCのつながりから、新しい出会いや海外での輸出や出店の話など、新たなつながりも生まれました。

西野さんの上場の目的は、一緒に働いている人たちの見聞録の最大化。 最初は、上場してお金持ちになりたいとの思いもあったそうですが、ステージが変わると「次にこれができる」と別の視点を持つ感覚になったそう。
学生さんへのアドバイス:アルバイト先への就職はNG
うちの学生アルバイトさんの中にも「このまま就職したい」と言う人がいます。ただ、僕は基本的にNGです。 理由は2点。まず、ご両親からすると、焼肉屋に勤めるために進学させていないだろうなと。 これは業界がまだ成長していないことも理由だと思います。まず、これが1つ目の観点。 もう1つは、新卒でしか入れない会社があるからです。 ベンチャーが求めているのは、どちらかといえば中途採用、戦力化されたメンバー。 キャッシュを生み出せない人間は、あまり活躍できない事実があります。 そういう意味では、最初からベンチャーを選ぶ必要はないんじゃないかなと。

選択肢が多い新卒だからこそ、今しか使えないカードを使った方がいい。 大手の場合、大手の会社の資本を使って勉強できる機会もたくさんあります。 新卒プログラムやジョブローテーションを通して自分の力を高めた方が、確率論が上がると語る西野さん。 学生さんに「そのままアルバイト先の飲食店に勤めるのは、あまり賛成できない」と言っているそうですが、反応はどうなのでしょうか。
「近江牛商社に1年いなかったら、置いていかれちゃう。あとで出戻りしようと思っても難しくないですか」と言ってくれます。 でも「たとえば本当に飲食が好きなら、海外事業を展開している、欧米・アフリカ・東南アジア含めて展開している企業に入社して、グローバルに2、3年仕事をやって、近江牛商社に戻ってきてくれたら」と新卒の子にはよく言いますね。

前提として、人間関係もできている。さらにそのスキルと経験があるなら、非常に稀有な存在です。 まさに高い年棒を払ってでも欲しい人材。 ただ、近江牛商社の成長速度の方が速く、その人よりもレベルが高くなっていたら、縁がなかったということです。
どちらにしても1回、外に出ること。 選択肢の幅が広いときに、チャレンジしておくと、自分が事業をするにせよ、何かを始めるときに大きな力になるということを伝えたいですね。
離職率はゼロに近い方が良いとのイメージを持っていましたが、離職率10%が適正数値であり、 社内の新陳代謝も必要だとの考え方に成長企業のエネルギーを感じました。 FUNDINOのサイトには、2022年以降のスケジュールが記載されています。 有言実行される姿、今後の動きも楽しみにしながら、数年後取材させていただければと思います。