今回お話をお伺いしたのは、一般社団法人インパクトラボ代表理事の上田隼也さん。
団体設立の経緯やインパクトラボ、コマースの事業内容、そして今後のビジョンについて気になる話をお届けします。イノベーションの究極は、起業
立命館大学在学中に、文部科学省のイノベーションプログラムを受講し、
イノベーションについて学んだ上田さん。 世の中には普及していない取り組みながら、自身が面白いと感じたことで、学校現場で取り組める仕組みをつくりたいと思うように。そのためには会社が必要。
僕は、イノベーションの究極は、起業だと思っています。 実際に自分でやってみてダメならやめればいいだけ。 全部、自分が実験台であり、ラボには研究室のような意味を込めています。
立命館大学だけでなく、世間一般でも「SDGs」を推す風潮が拡大。
学生活動として取り組んでいたものの、学生の活動には限界もあります。「起業も含めて視野に入れたら?」と言われたことで、最終的には自分の事業としてスタートさせました。
登記は大学卒業後ですが、在学中にほとんどの準備を終えていましたね。実際、ビジネスとしての方向性や事業の回し方については、
あまり想定していなかったという上田さん。 立命館の仕事を1個依頼されていたことで、起業を決意したそう。ただ、この仕事には拡張性があります。
立命館だけじゃなく、他の大学、学校、自治体など、取り組む中でいろいろ新しく閃いてきました。 いろいろ提案していく中で、ハマったものも多いです。嬉しいことに気づいたら雪だるま式に仕事が増えてきました。
ビジネスモデルのコアコンピタンスは、事業の設計力
もりやまキャリアチャレンジも含め、起業家育成は得意分野だと語る上田さん。
これまで、大学では起業家育成に取り組んでいたものの、高校生が経験する機会はほとんどありませんでした。守山市には、立命館守山高校、県立守山高校という場所があり、
守山市の担当者さん、立命館の先生も「ぜひやろう」と言ってくださった。 インパクトラボとしても「守山市の事業は新しい取り組みとして面白い」「特徴的な事業」とよく言っています。 「RSIF(立命館ソーシャルインパクトファンド)」をつくるプロセスにも関わりました。 これは、自分の中でもかなり大きな仕事です。 約10年の構想があったと聞いていますが、1年6ヵ月で具現化まで持っていき、 かなり時間短縮ができたと思います。
周りの方が「こんな未来ができたら」「こういう事業があればいい」と思う部分に対して、
事業を構想し具体的なモデルとして成り立たせてきました。僕は、考えて、アクションすることがものすごく得意です。
構想力、いわゆる想像してどうすれば具体的になるかをイメージして設計することが得意です、好きです。 これがインパクトラボのビジネスモデルの一番強いところです。学校のアクセラレーターのような存在として活躍する上田さん。
取材当日の朝も、Zoomを使用し、群馬県の高校生にオンライン授業を実施。 群馬県では県内の小中高校にパソコンやタブレット端末が1人1台配布されています。ストーリーを重視し、大学生、インターン生を採用
インパクトラボでは、アルバイトを雇用するのではなく大学生のインターン生が参加する仕組みが整っています。
これは、立命館大学のSDGsに取り組む学生プロジェクトの延長として始まっていることが大きな理由。これまでのインパクトラボができたストーリーに関係のない大人を連れてくることはできるだけ避けたかった。
大学生が成長できるような仕組みとして研究室をつくるスタンスだったので、その点にはこだわりました。インパクトラボの事業は、滋賀県内だけでなく日本の中にはあまりないモデルのため、
立命館の関係者とも話しながらつくっている段階。 アメリカの大学の研究室の場合、研究室に配属されると給料をもらいながら仕事をするケースが一般的だそう。 しかし、日本の大学の場合、教育の名の下に無償で働くケースが多いといいます。僕は、大学生やっている活動の全てに価値があると思っています。
だから、適切なお金を払うことが重要。そして、僕はマネジメントするプロとして、彼らをマネジメントできるように頑張っています。 大学生にはインパクトラボでは、できるだけ研究している認識で活動に取り組み、成果を出してもらう。 常に真剣勝負。次世代の新しい研究室、新しい大学の在り方を研究しているイメージです。
“新しいもの好き”な立命館大学のカルチャー
自由に動いている印象のインパクトラボですが、
立命館大学だからこそできることがあるといいます。基本的に、立命館大学という組織のカルチャーは、新しいことにチャレンジします。
未来を見据えながらチャレンジしている大学。 たまたま、僕のような新しいもの好きの人が、チャンスをもらい、得意な分野で関わる。 新規プロジェクトに関わることができる、そんな流れがあります。 総長を含めて多くの教職員の方がチャレンジをしている印象です。 ただ、常に結果を出さないといけないリスクはありますね。さらに上田さんは、2019年に「株式会社COMARS(コマース)」を設立。
大学時代、先生と一緒に特許を取得しました。
特許を生かし、知的財産のビジネスを大学発のベンチャーっぽくやったらカッコいいよねと話し、 自分の資金を使って会社を立ち上げたのが始まりです。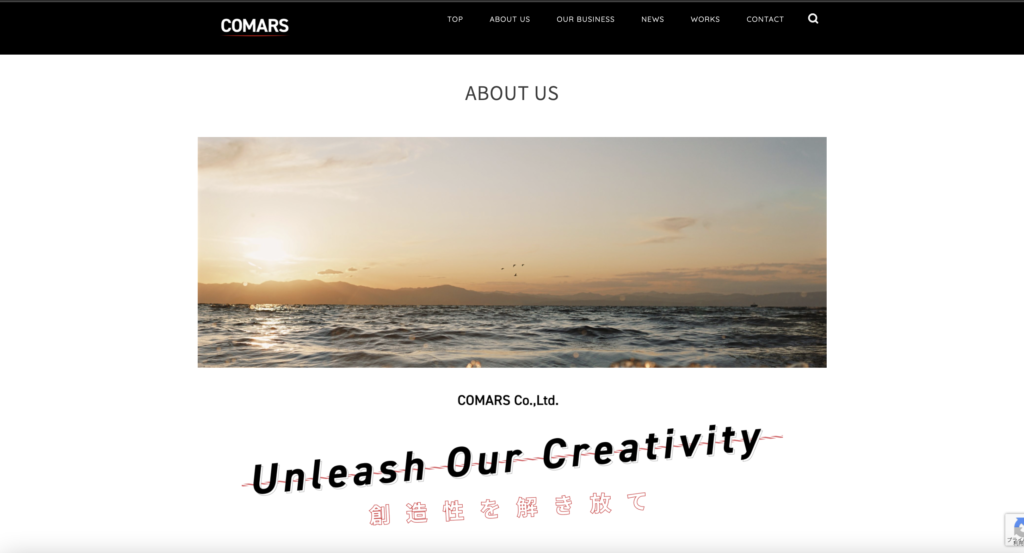
新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、映像需要が生まれました。
たまたま立命館大学映像学部の学生が「映像をつくりたい」と声をかけてきてくれたんです。
そのまま、会社を使って一緒にやろうと伝えると、うまくいって組織化されました。 世間的には事業のピボットですが、僕の中ではなるようになればいいと思っていただけ。 たまたま世の中のニーズがハマり、その結果うまくいっていると思います。インパクトラボとコマースの相乗効果
意図しないところでコマースの事業が成功する中、
改めてインパクトラボとの相乗効果を実感するという上田さん。インパクトラボでは、プロジェクトを構想し新しい事業をつくる。
コマースは、具体的に記録や映像としてカタチにして残すことができる。 エモさやふわっとしたものに対し、感情を動かすような映像をつくることができるので、 例えば、大学とは相性がいいと感じます。自治体との仕事、例えば教育、公共政策的な部分に関しては、
非営利法人のインパクトラボで対応するスタンスを貫いていますが、基本的にはコマースと一緒に取り組んでいます。 ただ、教育は成果が見えにくいため、映像で残しビフォーアフターを見せる工夫をしているそう。 日々色々な事業に関わる中で、うまくプロジェクトを回す秘訣をたずねてみました。僕は、起業家よりナンバー2の人をよく見るようにしています。
起業家は、口ではすごくエモいこと、いいことを言うんです。 でも、実際にプロジェクトを回すナンバー2が誰なのかで、うまくいくかどうかが変わります。これは、自分にも言えることです。 自分でもナンバー2にチームをうまく回すことができないと、多分、自分が大変なことになることを知っています。 「あ、プロジェクトが回っていない」と思ったら、いい人を探してチームに入ってもらいます。 これが秘訣です。まずは、自分自身が実験台です。
要となるナンバー2の存在がちゃんといてくれるからこそ、
さまざまな事業が同時多発的に始まったとしてもスムーズにプロジェクトを進めることができる。 もし、プロジェクトが回らなくなったら、そのときは、考え直したり仕事を一旦リセットしたりする必要があると思っています。起業した今思うこと、3年後のビジョン
起業してスタートアップなど、華やかな世界に行くまでには、思った以上に時間がかかります。
地道な時間。理想までに行くためには、地道な努力がめちゃくちゃ必要です。 テレビに出ているような、名だたるスタートアップの起業家、経営者になりたくて、 2、3年で実現できると思ったら大間違いだなと。 結構、そういう気持ちでやろうとしちゃったので、自分でも今となっては反省しています。スタートアップの経営理論よりも請求書の送り方、会計ソフトの使い方など、
起業には、地道で重要な部分があることに気づいたという上田さん。 今、周りにいる起業を目指している学生には、自分の反省も込め、バックオフィスの重要性を教えているそう。ただ、若い世代では、起業家志望というよりも
「動画をつくりたい」「面白いイベントを開催したい」と思っている方が多い印象です。 ただ、彼らがどう思っているかはわかりませんが、やれば絶対にうまくできる。 起業も自転車の乗り方と一緒で、最初の1年間で何をすればよいのかわからないんです。 世の中的にもそこがブラックボックスです。成功者しか知らないような世界になっている印象です。 でも、その思った以上に面倒くさい過程も含めて、全部見える化できれば、 学生たちも「俺でもできるんじゃね?」みたいに思うんじゃないかなと。 そして起業家が増えれば、社会は面白くなるのかなと。
守山市のキャリアチャレンジ、他の起業家育成プログラム。全てが学習教材。
インパクトラボがノウハウを蓄積させて、次に繋げていきたいです。 それは、関わっている人にもノウハウができます。インパクトラボでは、メンバーが違う場所で新しいビジネスを始めるのもOKです。
インパクトラボの中に留めておく意味はありません。これが、増殖型エコシステムです。 どんどん増殖させて、5年後や10年後に面白いことができるような 仲間が増えるといいなと思って取り組んでいます。1つの会社として売上を増やし、大企業をつくるのではなく、
自分達のノウハウをより多くの人に浸透させる。そして、社会が面白くなる。まさに、壮大な社会実験を繰り返してやっています。インパクトラボでは「利他的に物事を進めたほうが、売上も信頼も増える」です。
自分さえ良ければいいとの考えではなく、周りの人が喜ぶ方が、次につながる。 そして、新しい経済圏が生まれる。そんなスタンスで取り組んでいます。3年後も、利他的に生きていたいという上田さん。
ビジネスとしての売上が増えることも良いとしながらも、ソーシャルインパクトを重視する考えが根底にあります。社会的にいいことができる、みんながちょっと楽しいことができる。
そんな人たちが増えるように、後押しできればと思っています。
前編ではインパクトラボの事業やこれから目指す未来の方向性をお伺いしてきました。
後編では、上田さんの考える理想のチームや起業を目指す次世代の方へのメッセージをお届けします。
