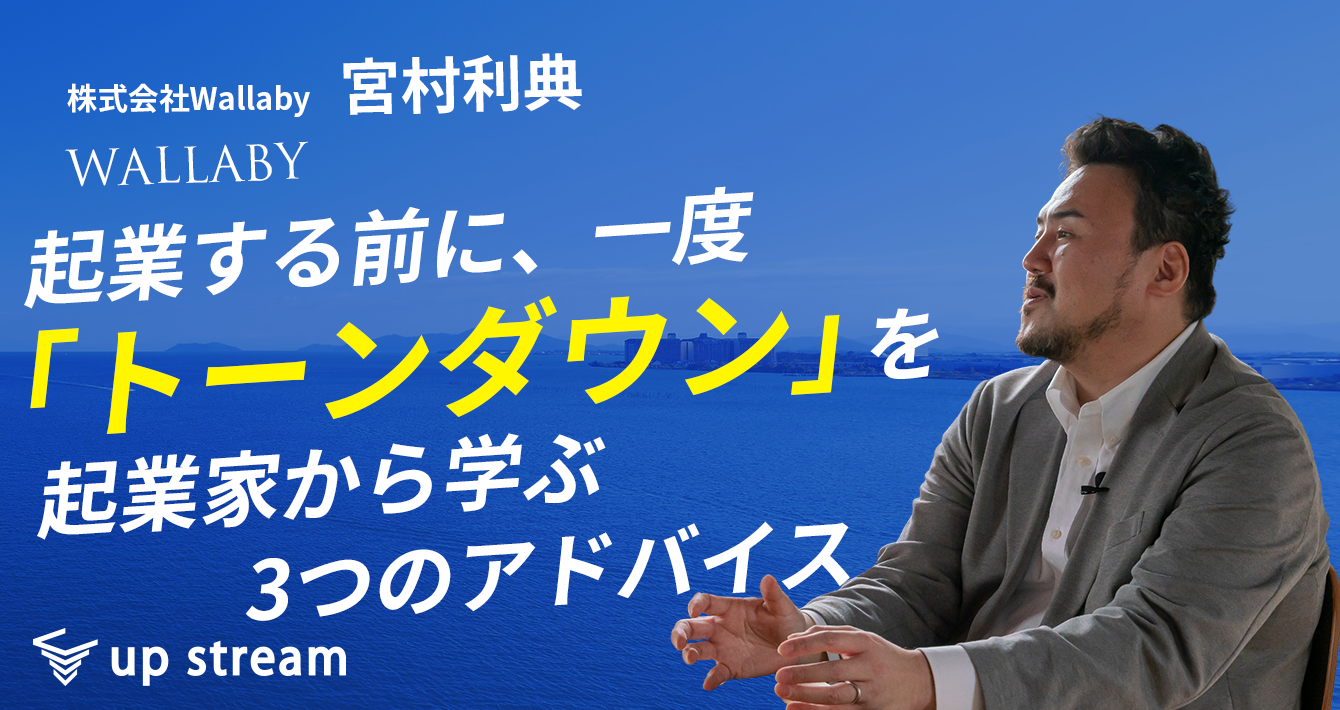前編に引き続き、株式会社Wallabyの宮村利典さんにお話を伺いました。 後編では、リスク回避のコツや失敗したこと、起業を目指す次世代の方へのメッセージをお届けします。
起業前に知っておきたい「リスク回避のコツ」
一般的には高リスクとなる、大規模の施設運営。 まちづくりは重要な事業ではあるものの、自分の生活も大切です。 チャレンジに対するリスク回避の秘訣について、たずねてみました。
まず、戦後、僕の祖父は不動産業を営み、晩年は自社物件の賃貸をしていました。 その後、父と僕が引き継いでいるため、小規模ながら自社物件活用をファミリービジネスとして行っていた実績があります。 新しい物件取得は、リスクを負うことです。 ただ、ゼロベースで酒蔵を購入し「さぁ、これからどうする?」という話ではありません。 祖父や父が築いてくれた土台があったおかげで、スタートのハードルは若干低くなったんじゃないかと。

多少なりとも土台がある状態でのスタートとはいうものの、 宮村さんの場合は、公務員を退職しての起業です。 準備段階において、重視したのが最低5年分の事業計画、資金繰り表の作成でした。
不動産や建物活用の場合、費用的な規模も大きくなります。 いくらリスクを小さくしたとしても、少しでもブレがあれば、一歩間違うとすぐに失敗につながってしまう。 事業計画、資金繰り表は、みなさん作っていると思いますが、いろいろシミュレーションしました。 なんとかうまくいく方法を考えつつ、リスクを計算した形です。 妻も公務員で同期のため、今も働いてくれています。 無茶はできませんが、僕に多少何かがあったとしても、なんとかやっていけるんじゃないかと。 全ての要素を使って説明したことで、家族も安心してくれました。
簿記の知識や資金繰りについては、全て自分で勉強したという宮村さん。 当初は決算書も自分で作成。 家族や銀行に見せる資料作成のほか、事業とは別に、家計のやりくりの計画表も作成したそう。
起業して思ったことは、お金が減るときは、一瞬、一気。本当に怖い世界です。 今でもその怖さがあるため、常に一生懸命考えています。

体が資本。組織活動の重要性。
会社設立から1年半後に宿泊施設をオープン。 実は、オープン直前に宮村さんは、一度倒れてしまったそう。 原因はおそらく過労かストレス。
「体が資本」とよく言いますが、健康は本当に大事。 特に会社の経営に関しては、すごく大事です。 特に最初は、ほぼ自分1人。僕と妹で動いていたので、僕が体を壊したら、それで終わりの状態です。 倒れたときは、なんとかスケジュールを全部変えて、おかげさまで乗り切らせてもらいましたが、健康の大事さを痛感しました。
特に事業を始めたばかりの状態では、自分が止まると全てが止まります。 支払いは必要のため、手持ちのお金が減ることは止まりません。その思いから、雇用の重要性に気付いたのでしょうか。
宿泊施設の清掃は、僕1人では当然無理ですので、パートタイマーの方に入っていただきました。 費用面だけで見ると、まだ微妙なところではあります。 ただ、雇用したことで奇跡的な出会いがありました。

最初は業務委託とパートタイマーとして契約した、元・ホテル経験者の方2名。 2年前から正社員として雇用。
単純に1+1=2になるのではなく、1+1=3、1+1=4ぐらいに できることが増えたのではないかという印象です。 今まで僕が思いつかなかったことが改善したり、僕は自分の得意な分野に時間を割くことができたり。 組織的活動により、新しい領域に入ることができました。

しかし、同時に組織活動ならではの難しさも。 人それぞれ、やりがいや目的は異なるもの。 みんなが気持ちよく仕事ができる環境をつくることが、パフォーマンスの向上につながります。
僕が今まであまり関わってこなかった組織づくり、という分野です。 面白さはありますが、すごく難しい仕事。みんなで成し遂げるためには、どうすればいいのか。 ずっと1人でやっていたので、今、初めて気づきました。 起業の形はさまざまですが、従業員を雇用するところまでいこうとしたら、組織づくりも必要。
起業準備の段階では、資金面や提供する商品、サービスが頭に浮かびます。 しかし、処理方法を考える際に「果たして1人でやるのがベストかどうか」の視点も必要だと、今、改めて感じるそう。 信用金庫の紹介により、滋賀県産業支援プラザを通じて中小企業診断士に対し、販路開拓などの相談を受けた宮村さん。 その縁から現在も月に1回面談を継続。 多方面からのアドバイスを生かしつつ、雇用調整助成金などの助成金も活用しているとのこと。
起業する前に、一旦トーンダウンしてほしいと思う理由
起業を考え、自分がやるべきことが頭に浮かんだら、 まずは、1日、2日ゆっくり考えることが大事だと思うと話してくれた宮村さん。 その理由は、起業した今だから思うこと、わかったことがあるそう。
世の中には、いろいろな人がいます。 行政の人、大企業から中小企業、金融機関、地元の人、UターンやIターンの人、それぞれがいろいろな活動をしている。 町屋の再生活用にも、みんなが関わる余地があります。 そういうことにも目を向けて、自分の役割は何かを考えたほうがいい。 自分の一番いい関わり方は何か、自分の居場所はどこかを考えるのもいいんじゃないかと思うこともあります。 たとえば、大企業や地元の銀行に勤めたり、公務員として働いたりしているなら、 発注先を地元で起業した新しい小さな企業に発注してみたら、今までと違う、面白い事業ができるかもしれません。 ちょっと見方を変えれば、起業したつもりで、大きな既存の組織の中でも、新しい動きができることもあるんじゃないかと。

企業内でスピンオフした組織づくりや副業も、数年前に比べると増加傾向にあります。 大企業に勤めながら、週に2、3回、コワーキングスペースで自分が設立した会社の業務を行うこともひとつの方法です。
起業とひとくちにいうけれど、いろいろなやり方があります。 その辺りを模索しつつ、すぐに起業するのではなく、周りも見つつ、今いる場所でもできることを少し考えてみる。 いろいろな可能性や方法がある中で、ぜひ、そのあたりを皆さんには模索していただければと思います。
起業を考えている方への3つのアドバイス
最後に宮村さんに起業を検討中の方にアドバイスをお尋ねしました。
僕も毎日変化している最中ですが、まず1つは、 想定でいいので常日頃から資金繰りをやっていく、試算しながらやっていくこと。 事業が事業として成り立つかという計算は、土台として重要です。 そして、2つ目は自分が最終的にしたいことを、発表する、人に話す。 具体的に資料をつくり、何か行動を起こす。 頭の中で考えるだけじゃなく、書いたり話したりして、外に見えるような形にすることが大切だと思います。

人に話し、行動することで、 同じ思いの人と出会う経験をこれまでに何度もしてきたという宮村さん。 「ちょっと無理かも」と思っていたことでも、口に出すことで、 同じ思いを抱いていた人と出会い、具体的に話が進んだことは何度もあるそう。
3つ目は、仕事の処理、作業体制を整えることです。 体を壊さないように、仕事を分担する。分担するための人件費も事業で生み出せるかどうかも同時に計算します。 総合的に判断して、できるかどうかを考える。できなかったらお客さまに迷惑がかかります。 そうするともう、なんのために事業をしているのかわからなくなりますよね。 無理ならむりで、別の人にお渡しする。できない部分からは退場することも大事だと思います。