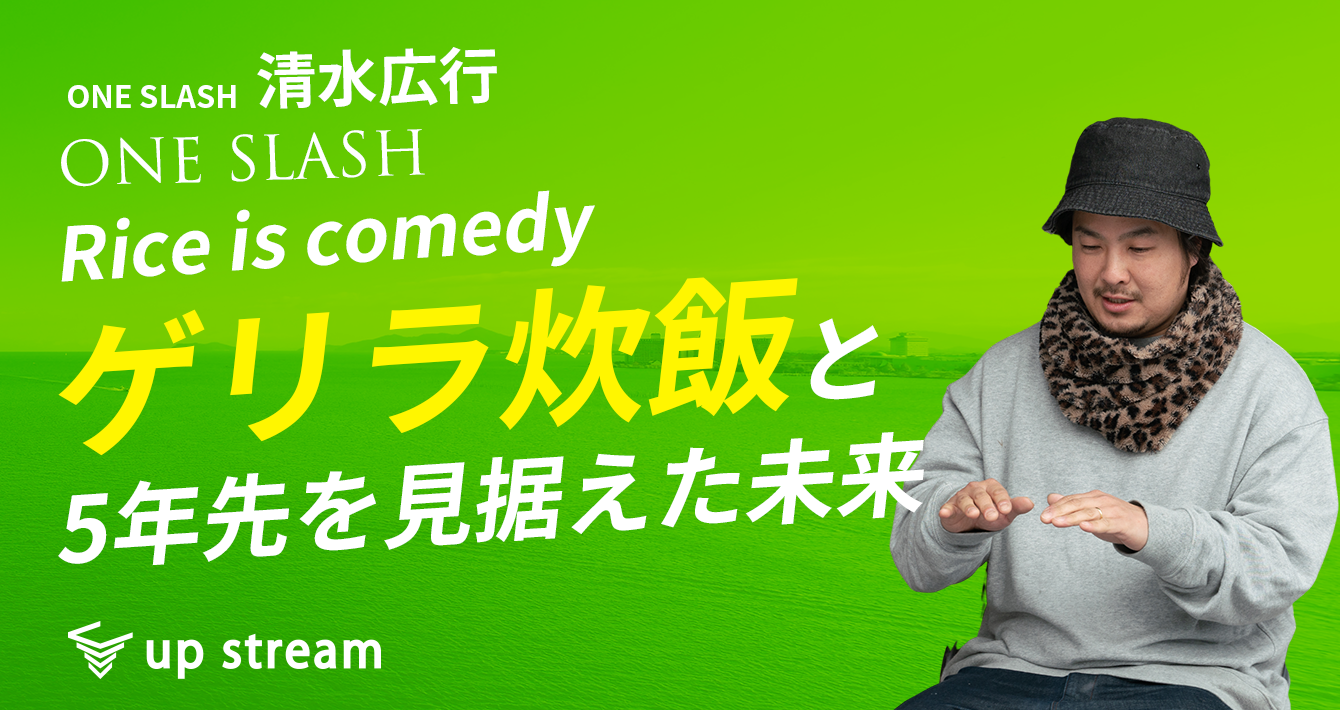今回お話をお伺いしたのは、ONE SLASH代表の清水広行さん。 団体設立の経緯や「ゲリラ炊飯」誕生のきっかけ、方向性がブレることなくチャレンジを続けられる理由、 そして今後のビジョンについてお話を聞いてきました。
Rice is comedy(米づくりは喜劇だ)
家業である建設業を継ぐために、30歳で地元・西浅井にUターンした清水さん。 実は、地元の同世代と「地元で何かをやりたい」との話が出たのは、25歳ごろのことでした。 いつか何かを始めるため、少しずつ準備を開始。 しかし、最初からお米づくりを意識していたわけではなかったとのこと。
最初の事業計画は、不動産です。 今のコンセプト『Rice is comedy(米づくりは喜劇だ)』では見えていない、 後ろでしっかりビジネスとして柱が立つマーケットを選んでスタートしました。 ただ面白いことをやるなら簡単です。だからこそ、面白さだけで終わらず、ビジネスとして持続可能な事業をしたいと思っています。

『RICE IS COMEDY』のすごいところは、販売しているお米の8割以上が、BtoCであること。 初期段階から、ファンに向けて継続的に販売しているイメージがあります。
既存の農業システムは、すでに崩壊していると思います。 難しい方法にあえて突っ込んでいく必要もないかなと。 そもそも、僕たちがお米づくりを始めようと思ったのは、地域のお米が武器だと思っていたから。全国で戦えるくらいうまい米ですから。
昔、スノーボード選手として全国各地に行き、海外で暮らした経験もある清水さん。 各地の米や日本酒を味わう中で、地元の米は日本有数の米どころと比べても全く劣らないと感じていたそう。
そもそも、昼夜の寒暖差がある地域のお米がうまいというのは周知の事実です。 ただ「うまい」は抽象的で、人の好みですよね。 そこで専門機関にお米のおいしさをはかる「食味値スコア」の計測を依頼しました。

食味値スコアとは、お米の水分やタンパクを数値化したものです。 一般的に日本の平均値は65〜75点、一流のお米が80点といわれています。
1年目、初めて西浅井でつくった米を調べてもらったら、93点が出たんです。 僕たちも、検査員の方も驚いた。ノウハウもなく、近所の人たちに聞きながら、初めてつくった米が、93点。 これは、もうお米の点数やうまさを全面に押し出す売り方はやめようと思いました。
高評価の数値が出れば、その数字を押し出したくなりそうなものですが、清水さんたちは他の売り方を選択。 今振り返っても、いい戦略だったと感じるそう。
お米って、みんなおいしさを全面に押し出して売っているんですよね。 だから、レッドオーシャンに見えるんです。 でも、その路線を外したらブルーオーシャンですよ。これが、僕たちの一番の勝因だと思っています。

おいしいお米であることは証明できた。 93点は、あくまで切り札。切り札を前に出す必要はない。 まずはファンをつくり、その奥で地域を応援してもらえるような農家になろう。 そして『RICE IS COMEDY』が始まります。
ゲリラ炊飯と結果論の「地方創生」
農業を始めることで、さまざまな出会いがあり「米だけじゃなくて、 野菜もつくれる?」と声をかけてもらう機会が増えるように。 しかし「野菜もつくれるかも」「一度やってみようか」と考える中で、清水さんの心境に変化が現れます。
自分の中で、全然面白くないなって。 「今、めっちゃブレてる」と思ったんです。そこで、もう一度米づくりに特化しました。 でも今度は「売る」にブレだして。でも、ブレたら戻す、定期的に原点回帰するのが僕たちのやり方です。
全員が集まり、お酒を呑みながら頭を柔らかくしてしゃべるのがONE SLASH流。 ある日、呑みながらしゃべっている中「いきなり街の中で米を炊いたら、面白いんじゃないか」と、ゲリラ炊飯のアイデアが誕生。 翌日ホームセンターへ行き、道具を購入。 薪を用意して炊いてみたところ、最高においしい。 さっそく商店街の方にイベントの許可を交渉し、曳山博物館で開催。
ただ米を炊くだけじゃ格好つかないと、櫓(やぐら)もつくりました。 ガラガラと音をさせながらやるのって面白いでしょう。 材料は、仲間の大工さんの工場(こうば)の廃材です。 そもそも地方創生とか、まちをよくするというのは結果論。 自分たちが面白いと思うことをやってみたら、周りがもっと面白く思ってくれた。だから活気が生まれたんじゃないかと。

一見、計画的に見える清水さんたちの行動ですが、計画的に地方創生を目指すのはかなり難しいといいます。 もし、最初からできるなら、日本各地に「地方創生」の課題は生まれないはず。 本陣としての面白さの追求と、面白い部分に人が集まる図と体制づくりが重要です。
新しいチャレンジを続けても、方向性が決してブレない理由
ゲリラ炊飯イベントを重ね、地域を活性化させるONE SLASH。 お米のおいしさやアイデアも相まって、多くのメディアにも出演。 今では、長浜エリアだけでなく、他の地域からも注目を浴びています。 しかも、全員が地元のメンバー。方向性がブレる、ズレるといったことはないのでしょうか。
なぜブレないか。 これは、最初に始めるときに全員から “人質”をとったんです。 決して危ない話ではなくて “地元”という人質です。 これはもう魔法の言葉。「地元のためにやるんやで」って。家族のため、子どものため。 根本的な欲求のところに重きを置いているんです。だから逃げられないんですよ。

清水さんいわく、米づくりはただの手段。他の事業もただの手段。 やっているのは「地域で盛り上がる「地域で稼ぐ」「地域で自分の子どもたちとの時間をたくさんとる」こと。 そして向かっているのは、本来の豊かさ、本来のライフワークバランス。
僕たちには「お前ブレてるやん」「あ、ブレてるな」と、仲間で言い合える関係があります。 でも、ブレてもいいんです。ブレてもいいから、その後にちゃんと戻せる仲間でいましょうと。 その関係を築いたまま、人数が増えれば、大きなムーブメントを起こせると思っています。
県外に広がるムーブメント。5年先に目指したいもの
現在2022年。5年後の2027年、清水さんが見据えている未来についてお伺いしました。
一旦、“地域”を全部横に置いて話しますね。 まず「地域」「市」「県」といった縛りをつくってしまうと、認知はその中でしか広まりません。 でも、僕たちのやっていることは、世界にも通用すると思っています。 たとえばお米も、長浜市、滋賀県、日本と広がっても十分勝負できます。 同じ感覚で、日本の文化は世界で通用するとの視野でやっていきたいんです。 だから、5年後はニューヨークのど真ん中でゲリラ炊飯とか。 最初の目標は、「GUCCI」のレセプションパーティでゲリラ炊飯。 世界のセレブにジャパニーズカルチャーを食らわせたい。レディ・ガガに、おにぎりを「どうぞ」と手渡したい。 そうするとどうなるか?放っておいても、地域は盛り上がる。 「よくわからないけれど、西浅井という場所で僕もお米がつくりたいです」という人が必ず来る。

「予想できている時点でやる必要はない」と語る清水さん。5年後、2027年が楽しみです。
前編ではONESLASHの事業やこれから目指す未来の方向性をお伺いしてきました。 後編では、清水さんのよりパーソナルな部分や起業を目指す次世代の方へのメッセージをお届けします。